まだ街が眠っている早朝。氷と魚のにおいが漂う市場では、一日の始まりを告げるリズムが生まれる。
発泡スチロールの箱がすれる音、魚を運ぶ掛け声、次々と積み上がるコンテナ。そこには、普段の生活ではなかなか感じられないエネルギーがある。まるで朝日が水面を染めていくように、自分の中にも活力が広がっていく。
九州魚市株式会社は、北九州を中心に魚市場を運営し、人々の食を支えている会社だ。早朝から新鮮な魚を仕入れ、食卓に届けるまでの流れを担っている。普段の生活では直接目にすることが少ない場所かもしれない。だが、ここでは若手社員も新しい挑戦を広げながら働いている。今回は、そんな市場で活躍する人たちの姿を紹介します。
「こんな私でも大丈夫」と安心して働ける環境

最初に登場するのは、入社6年目の隈部(くまべ)さん。高校を卒業してすぐに入社し、現在は管理部門で経理や人事を担当している。
「早く働いてお金を貯めたい」と考えていた高校時代。進学は選ばず、就職を選んだ。「やりたいことを楽しむためにはお金が必要。だったら働くのが一番」と考えてのことだった。
ただ、最初は早朝の勤務に不安もあったという。もともと朝が苦手だったからだ。しかし実際に働いてみると、朝が早いぶん昼過ぎには退勤でき、夕方以降の時間を自由に楽しめる生活リズムにすぐに慣れた。ライブや買い物、友だちとの時間も充実。「もう9時〜17時の勤務には戻れないかも」と笑うほど、この働き方が気に入っている。
支えとなっているのは「人間関係の良さ」だ。もともと人と話すことが好きな隈部さんは、最近では採用担当として合同企業説明会などにも参加。自分の言葉で会社を紹介し、「面白そう」と感じた学生が実際に入社を決めたこともある。「誰かの背中を押して、人生が動く瞬間に立ち会えたのは大きなやりがい」と語ってくれた。
若手もベテランも、どちらもが輝ける場所

「入社前は市場ってちょっと怖そう、職人気質の人が多そうというイメージでした」
そう話すのは、セリ場で働く入社2年目の馬場さんだ。市場といえば「体力勝負」「男社会」を想像していたが、実際には違った。先輩たちは優しく、分からないことは丁寧に教えてくれる。眠気はあるが、新しい発見や学びがあるから毎日が楽しいという。
一方、加工品の部署で12年目の赤池さんは「市場は人と人の支え合いで成り立っている」と語る。忙しいときは助け合い、休日には“釣り部”を結成して一緒に海に出ることもある。
普段は電話対応や管理業務に追われる赤池さんも、「自分が扱った商品がスーパーに並んでいるのを見ると嬉しい」と話す。過去にはノルウェー産のアジを日本一仕入れていた時期もあったという。「毎日違う魚が入ってきて、それをその日のうちに出荷するスピード感が自分には合っている」と笑顔で話してくれた。
馬場さんはセリの現場で働くうちに、「競り人になりたい」という目標を持つようになった。買参人とやりとりしながら価格を決める競り人は市場の花形。近い将来、その場所に立ちたいという夢ができた。「自然と“なりたい姿”が見えてくるのも市場で働く魅力」と語る。
社長が想い描く「22世紀の市場」の姿
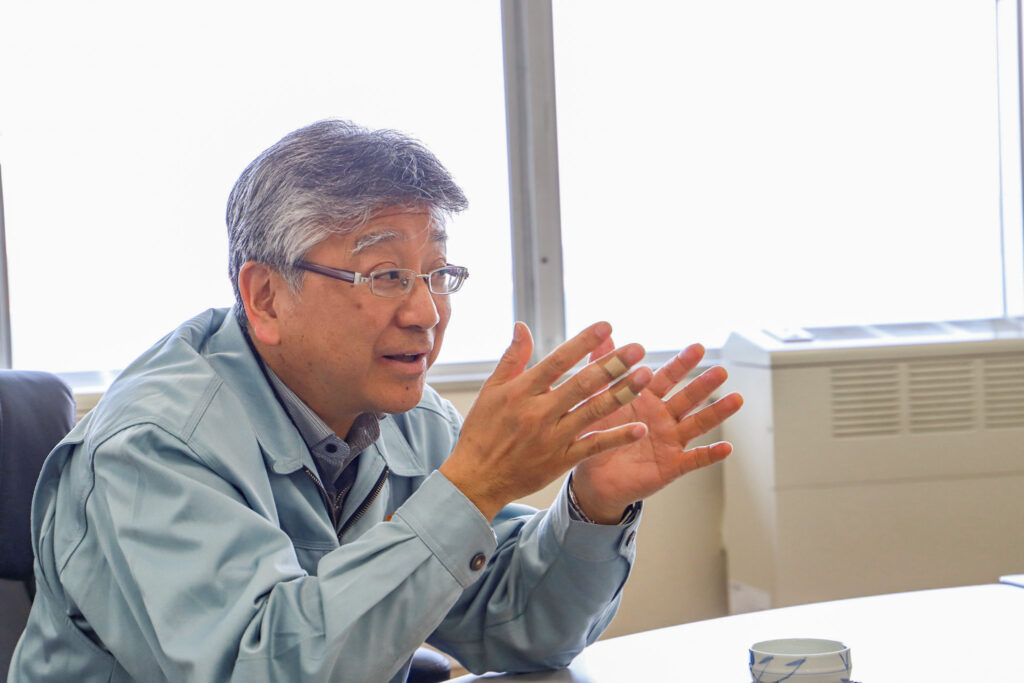
市場をもっと開かれた場所にしようと、ここ数年「22世紀委員会」という若手中心のグループが活動を始めている。発起人は社長の中谷さんだ。
最初は仲間同士で集まる飲み会から始まり、次第に「イベントをやってみよう」と声が上がった。JRとのウォーキング企画、地元大学とのコラボ、市場まつりなど、次々にアイデアが形になった。数千人が参加した市場まつりの成功は「市場にこんなに関心を持ってもらえるんだ」と大きな驚きと自信につながったという。
社長は「上から“やれ”と言うだけでは続かない。若手が自分で考え、形にしていく方が楽しいし成長につながる」と考え、イベントの運営は若手に任せている。サポートが必要な交渉ごとは社長が受け持ち、自由な挑戦を後押ししている。
22世紀委員会の目標は「早起きするだけの市場ではなく、新しい面白さを発信する市場」。セリの見学ツアー、マグロ解体ショーの配信、サッカーチームや高校生とのコラボなど、アイデアは尽きない。ベテラン社員も「楽しそうだから手伝う」と参加するようになり、次第に輪が広がっている。今後は職場体験や校外学習で高校生を招くことも計画しているという。
歴史と挑戦、その両方を楽しむ場所

市場で働く魅力のひとつは、そこに積み重ねられた歴史と知識だ。漁師や仲買人は魚や海に詳しく、旬の魚や美味しい食べ方、土地ならではの“通”な知識を教えてくれる。それが私たちの日常を彩ってくれる。
そして市場での仕事は「魚を扱う」だけでは終わらない。イベントの企画、広報活動、海外発信など、やりたいことを見つけながらチャレンジできる。赤池さんも「最初は魚の知識がなかったけれど、新しい業務に挑戦できるのが面白い」と語る。
社長も「若手にはアイデアをどんどん試してほしい。失敗しても大丈夫。そこから市場の新しい可能性をつくっていってほしい」と期待を寄せる。
新鮮な驚きが毎日にある
「魚が大好きじゃなくても、働いているうちに自然と興味が出てくる」と隈部さん。迫力あるセリや仲間とのチームワークに魅了されてしまう人も少なくない。
赤池さんも「新人の頃は“セリって何?”という状態でも、先輩が丁寧に教えてくれた。だから安心して飛び込んで大丈夫」と言う。市場は横のつながりが強く、大変さもみんなで分かち合うからこそ楽しさがある。
北九州市の“台所”を支える市場には、まだまだ知られていない魅力がある。朝が早い、体を使う仕事というハードルを感じるかもしれないが、そこで働く人たちは「もっと面白くしよう」という想いにあふれている。イベントで地域とつながったり、釣り部で盛り上がったり、セリの最前線に挑戦したり……。魚と同じように、毎日新しい発見が転がっている世界だ。
「自分は朝起きられるかな」「魚の知識がなくても大丈夫かな」と不安に思っても、まずは見学してみてほしい。フォークリフトが走り、掛け声が飛び交うセリ場の迫力は、写真や映像だけでは伝わらない。
髪色の自由や若者同士の交流イベントといった“ゆるさ”もあれば、食文化を支える“真剣さ”もある。柔軟さと安定感のバランスがある場所だ。未来の自分は、セリの花形として声を張り上げているかもしれないし、加工技術を研究しているかもしれないし、海外に市場の魅力を伝えているかもしれない。
朝が早い分、午後を自由に楽しめる暮らしも魅力のひとつ。朝日を浴びながら響く掛け声の中で、新しい自分に出会えるかも。













