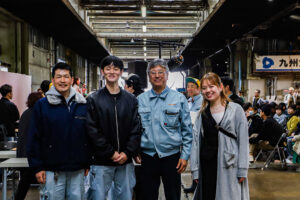みなさんは、道路や橋がどうやってできるのか考えたことがありますか?
毎日歩いている通学路や、新しくなった近所の橋。そこにどんな人たちが関わっているのかを知らないまま過ごしている人は多いかもしれない。土木と聞くと「重たいものを運ぶきつい仕事」というイメージから、自分には合わないと思ってしまう人もいるだろう。
でも、実際の土木はそれだけではない。ITや新しい技術を取り入れながら、人々の暮らしを支えるために進化を続けている仕事なのだ。
今回紹介するのは、道路や橋、河川の保護といったインフラ整備を行う藤木建設株式会社。特に「現場管理」というポジションを中心に活動している会社だ。
現場管理と聞くと、怖い管理者が厳しく指示を飛ばす姿を思い浮かべるかもしれない。もちろん現場の安全を守るために厳しさも必要だが、それだけではない。実際にはチームで協力するためのコミュニケーションがとても大切で、雰囲気も明るい場面の方が多いという。
土木は「キツイ・汚い・危険」の“3K”のイメージだけで判断するにはもったいない仕事だ。完成した道路や橋を見て「これ、自分がつくったんだ」と思える誇らしさは、ほかでは味わえない。高校を卒業して資格を取りながら一人前を目指す道も開けている。
今回は社長と現場で働く社員に、土木のリアルな魅力を聞いた。
やりたいことが諦められなくて

最初に話を伺ったのは速水さん。お兄さんに誘われて前職から転職してきた。
高校時代は土木科に通っていたが、卒業後は建築系の会社に就職。思い描いていた仕事とのギャップに悩んでいたという。
「前の会社に入ったとき、自分が想像していたのと違っていて…。でも藤木建設でアスファルトを敷いたり側溝をつくったりする様子を見たとき、『これが自分のイメージしていた土木だ!』とワクワクしたんです」
印象に残っているのは、初めて任された現場だ。工期の半分が終わった状態から参加し、右も左も分からないままスタート。それでも3か月後に無事完成したとき、大きな達成感に包まれた。
「『自分に続けられるのかな』という不安はあったけど、終わってみたら『ここは自分がやったんだ』と思えるのが本当にうれしかったです」
現場は体力勝負ばかりではない。工期の管理次第で残業を減らすこともでき、オフを大切にできる。
「同じ場所にずっといるんじゃなくて、現場が終われば次の場所に移動する。外の空気を感じながら働けるのが魅力ですね」
同じ現場は一つとしてない、オーダーメイドな仕事

続いて話してくれたのは、20年以上働くベテランで速水さんのお兄さん。今では会社を支える存在として大きな現場も任されている。
「昔は日曜日しか休みがなくて、今でいう“ブラック”だったと思います。でもそれが普通だと思っていたし、必死でした」と笑う。
それでも続けられたのは、完成したときの喜びが大きかったからだ。道路や橋は何十年も残るもの。家族と車で出かけるとき、自分が手がけた橋を通るたびに誇らしい気持ちになるという。
「うちには直営部隊があるので、現場管理者の裁量が大きいんです。雨で工期が遅れたら職人を増やすか、作業時間を調整するか。そうした判断で自分たちの働き方も変わります。休みを取りやすくする工夫もできるんですよ」
若手を育てるうえで大切にしているのは「分からないことをそのままにしない」ことだ。
「分からないことが分からない、という状態でも大丈夫。周りに聞いて整理していけばいい。今はITで図面や測量も簡単になっているから、昔より成長しやすいと思います」
家業を継いだが、いつの間にか天職に

社長は、家業を継ぐ形で土木の道に進んだ。専門学校で学び、別会社で修行を積んだあとに戻ってきた。
「始めはやりたくて選んだわけじゃなかったんです。でも地元の道路や橋をつくるうちに『これは地域を支える仕事なんだ』と気づきました。それからは街づくりにも興味が広がりました」
社長によると、土木はまだ“3K”のイメージが残っていて若手の採用は簡単ではないそう。しかし実際はITや機械化で昔より働きやすい環境になっている。
「うちでは管理も直営部隊もあるので、管理をしながら重機を動かす経験もできます。『自分の現場』を任されるようになると裁量も増えて、若いうちからキャリアを広げられるんです」
頭を使い、体も動かす現場管理という仕事

土木や建設と聞くと「重たいものを運ぶ体力勝負の仕事」というイメージが強いかもしれない。けれど、現場管理の仕事はむしろ頭を使う部分が多いのが特徴だ。
あらかじめ決まっている完成までの期限、工期に向けて、天候や地盤の状態を見極め、必要な職人の人数や重機の台数、作業の段取りを考える。雨で作業が遅れたときには「このまま予定通り進められるか」「別の方法に切り替えるべきか」と判断し、計画を立て直すこともある。逆に順調に進めば工期を早めに終えることができ、その分休みを増やすこともできる。うまく采配がはまれば現場はスムーズに回り、働く人たちにもしっかり休暇を確保できる。だが判断を誤れば突貫工事となり、休日返上で走り回らなければならない。だからこそ、自分の決断が現場全体に大きく影響する“采配の面白さ”があるのだ。
また、建設業界全体では今、働き方改革が進んでいる。藤木建設でも、ITを活用した工程管理ソフトや高性能な測量機器の導入によって、作業効率が向上している。書類はペーパーレス化が進み、年間休日数を増やす取り組みや有給休暇の取得を奨励する制度も整っている。昔のように徹夜や夜勤が当たり前だった環境からは、大きく変わりつつある。
キャリアは自分の手でひろげられる

現場管理者として独り立ちするには、施工管理技士といった資格の取得が必要だ。二級は実務経験をおよそ2年積めば受験でき、合格すると正式に現場管理者として登録される。そうなれば給料が上がる可能性も高くなる。さらに経験を重ねて一級を取得すれば、任される現場の規模や責任も大きくなり、自分のキャリアの幅がぐっと広がる。重機の免許などを取れば、管理の仕事とあわせて自ら機械を動かすこともでき、より専門性を高めていける。興味や得意分野に応じて、自分らしいキャリアをつくれるのがこの仕事の魅力だ。
また、公共工事は単に道路や橋をつくるだけではない。災害が起こったときには、被災地の復旧を担う最前線に立つこともある。地域の暮らしを守るインフラ整備は、社会にとって欠かせない大切な役割なのだ。
社長自身も、街づくりの会議や行政との連携に積極的に関わりながら、「どんな道路や施設があれば安心・安全な暮らしにつながるのか」を考えている。近年注目されるSDGsや環境への取り組みもあり、インフラ整備の仕事はこれからますます重要になっていく。
地図に残る仕事に挑戦しよう
今回の取材を通して藤木建設は「若いうちに大きな仕事に挑戦したい」「自分の手でモノをつくりたい」「地図に残る仕事がしたい」人にぴったりの会社だと感じました。
最初は覚えることが多くて大変かもしれない。でも経験を積み、資格を取れば年齢に関係なく現場を任される。自分の判断で働き方をコントロールできるのもこの仕事の魅力です。
泥だらけのイメージがあるかもしれないが、実際にはITや機械を使うシーンも多い。季節を肌で感じながら、頭と体をフルに動かす日々の先には、自分がつくった道路や橋が何十年も残る。
「手に職をつけたい」「大きなモノづくりに挑戦したい」― そんな思いがあるなら、ぜひ土木を選択肢に入れてみてほしい。学校や部活では味わえないスケールと達成感が、ここにはあります。